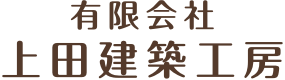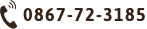三木金物祭り
2025.11.07
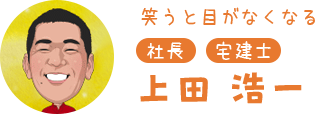
いつもお世話になっております。上田建築工房の上田です。
木々の葉も見事に色づく季節になりました。朝晩の寒さにはどうぞご用心くださいませ。
さて、11月2日(日)に兵庫県で開催された『三木金物まつり』に参加するため、大工さんたちと事務所へ集合し、4年ぶりに三木市へ訪れました。
今回は、大工が1級大工技能士の資格を取得するにあたり「道具を充実させたい」という要望があったことや、私の兄のもとで大工をしている甥が2級大工技能士の受験を控えており、必要な道具を揃えたいとのことで弊社の大工2名と甥と私の4名で「三木金物まつり」に参加してきました。
当日は“快晴”との予報でしたが、現地では少し雲が広がっており、屋外の販売ブースや飲食コーナーを回るにはちょうど良い気温で、楽しく見て、食べ歩きをしながら過ごしました。
現在私は大工仕事から離れており、今回はみんなの“運転手”として同行しました。
しかし、私自身も大工道具には強いこだわりがあり、若い頃には給料が安い中、思い切って14万円も出して鉋を購入したことがあります。いまではその鉋が25万円ほどに価値が上がっており、「自分の見る目も悪くなかったな」と少し誇らしく思っています。
最近、大工道具の話で面白かったのは玄翁(金槌)の話です。
ある職人が10万円の玄翁を購入し、ケヤキとアクリルボードで専用ケースを作って、その姿を眺めながらお酒を飲むのが最高の楽しみだというのです。
実際に見せてもらうと、その道具への愛着とこだわりが伝わってきました。

近年は、鉋や鑿を使う仕事は減っています。
しかし技能士の試験には欠かせない道具であり、特に鉋は「仕込み」ができていなければ美しい仕上がりにはなりません。仕上げ砥石も相応のものが必要です。
では、なぜ今もなおこの技術が必要なのか。
それは、地域に残る重要文化財や木造建築の保護・修復など、「建てる」だけでなく「守る」ことも大工の大切な使命だからです。
そして、彼らの高い技能こそが、上田建築工房の大工職人という“人づくり”において欠かせない柱となっています。
そうした思いを胸に、日々技を磨く職人たちを支えられることに感謝しています。
当日は鉋や鑿の職人の方々と久しぶりに話すことができ、数年ぶりにも関わらず覚えてくださっていたことに嬉しさを感じました。
買い物を終えたあとは、帰り道に世界遺産・姫路城へ立ち寄り、2本の20mを超える大黒柱を見て、職人の技に改めて感銘を受けました。

これからも「喜ばれる仕事」を続け、次は新潟へ鉋を見に行こうと盛り上がり、帰路につきました。

すべてに感謝