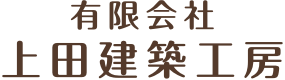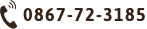南海トラフ巨大地震②
2025.03.14
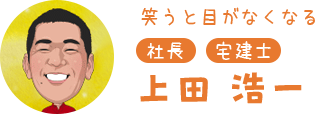
いつもお世話になっております。
上田建築工房の上田です。
今回は、前回に続き、南海トラフ巨大地震と能登半島地震について
書きたいと思います。
3月7日(金)の『タモリステーション』で「南海トラフ地震」の特集が放送されましたが、皆さんご覧になりましたでしょうか?
今後30年以内にマグニチュード8〜9クラスの地震が発生する確率が、約80%とされる南海トラフ地震。
最悪の場合、東日本大震災の約17倍、約32万人の死者がでると想定される、巨大地震にどう向き合うべきかという内容でした。
私が住む岡山県は、これまで比較的災害が少ない地域とされてきました。
しかし、2018年の西日本豪雨では大きな被害を受け、当時は、高速道路や180号線などの主要幹線道路が通行止めになり、約2週間孤立状態が続きました。
この経験を経て、私自身の仕事である建築の分野でも、職人の育成や災害に強い建物づくりの重要性を自覚しました。
「100年に1度の災害」「想定外」などという言葉をよく覚えておきますが
結局のところ、自分の命は自分で守るしかないと痛感させられた経験でした。
さて、令和6年能登半島地震は、1月1日16時10分に発生しました。
震源は半島北端にあたる珠洲(すず)市の深さ16kmとされ、輪島市と志賀(しか)町では被害7を観測。
周辺の地域でも震度6強を観測し、北海道から九州にかけて震度1の揺れが確認されました。
内閣府の発表によると、11月26日までに確認された死者・行方不明者は
462人(うち災害関連死者が235人)、負傷者は1345人にのぼるそうです。
また、住家の被害は全壊が6437戸、半壊が2万3086戸。
停電は最大で約4万戸、断水は約13万6440戸に及びました。
さらに、道路は路面の損壊や土砂崩れなどによって寸断され、救援活動にも大きな影響が出ました。
NHKが発表した人口推計によると、能登半島地震から1年が経った2025年1月1日時点で
最も被害が大きかった輪島市と珠洲市では、それぞれ2192人(10.0%)、1198人(10.2%)減少。
さらに、2月3日のデータでは、65歳未満の人口は輪島市で30%減、珠洲市で38%減。
65歳以上の人口も輪島市で26%減、珠洲市で32%減と、大幅な減少が報告されています。
また、地震基準と被害の関係を示すデータが発表されました。
能登半島地震で住宅被害があった輪島市、珠洲市、穴水町の調査によると
1981年以前の「旧耐震基準」の住宅では、倒壊・崩壊が19.4%、大破が19.8%と、高い割合を占めており、1981~2000年「新耐震基準」の住宅では、倒壊・崩壊が5.4%、大破が11.5%と減少しました。
2000年以降の「現行の耐震基準」では、倒壊・崩壊が0.7%、大破が1.3%と、被害が大幅に軽減していることがわかります。
この傾向は2016年4月に起こった、熊本地震でも同じでした。
益城町中心部の調査データを見ても、能登半島地震と同様に耐震基準が新しくなるほど、被害が軽減されています。

出典:国土技術政策総合研究所ホームページ
https://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn1296.htm
https://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0929.htm
能登半島地震や熊本地震では、倒壊・崩壊した住宅の多くが古い耐震基準の住宅でした。
建物の耐震性能が向上することで、倒壊・崩壊や大破した住宅が減少し、耐震基準の向上が効果的であることがわかります。
このデータをみると改めて、性能向上の大切さに気付かされます。
すべてに感謝